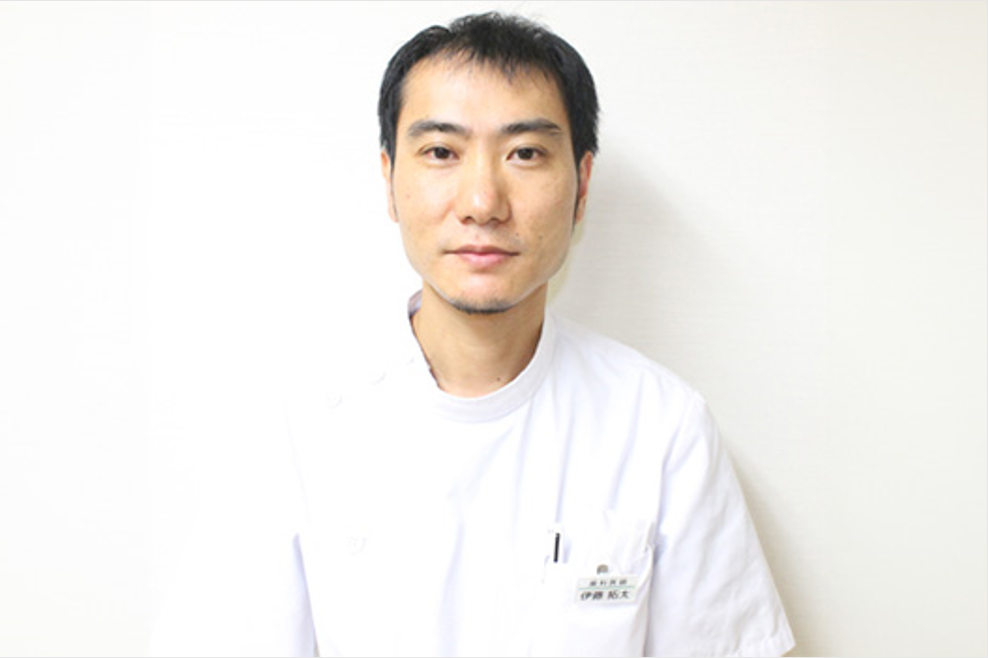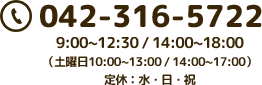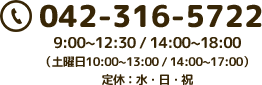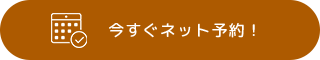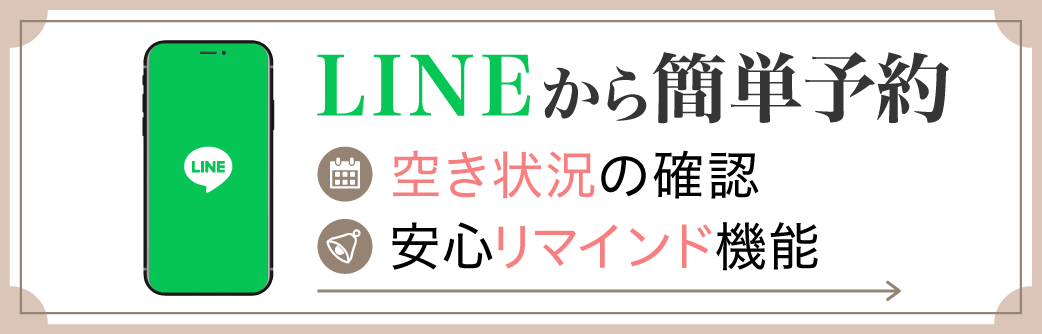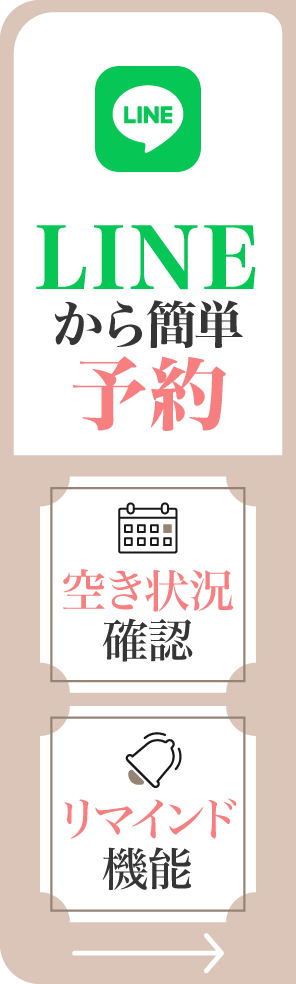歯医者の定期検診が高いのはなぜ?無駄な出費を防ぐ方法とは2025.03.05

定期検診は歯の健康を守るために大切ですが、費用が気になることもあります。
保険が適用されても、検査の内容によっては思ったより高くなることも。さらに、通院の回数が増えたり、自費診療が加わったりすると負担を感じやすくなります。
できるだけ費用を抑えたいなら、保険が使える歯医者を選び、自治体の検診制度を活用するのがおすすめです。
自分に合った頻度で通いながら、無駄な出費を減らす工夫をしてみましょう。
「歯医者の定期検診が高い…」と感じるのはなぜ?
歯医者の定期検診は、健康のために大切ですが、思ったより費用がかかると感じることもあります。
保険が適用されても、検査や処置の内容によって金額が変わるため、予想以上の支払いになることも珍しくありません。
さらに、定期的に通うことで負担が増えたり、保険と自費診療の違いが分かりにくかったりすることが、高く感じる理由のひとつです。
1回ごとの費用が意外と高いから
歯医者の定期検診にかかる費用は、保険が適用される場合でも2,500〜3,000円くらいが一般的です。
ただし、検診の際にレントゲンを撮ったり、歯周病のチェックや歯石取りをしたりすると、さらに1,000〜1,500円ほどかかることがあります。
結果的に、1回の検診で4,000円以上になることも珍しくありません。
また、予防のためのクリーニングやホワイトニングなどは保険が適用されないので、自費診療だと1回あたり10,000円以上かかることも。
保険の範囲で受けられる検診は、基本的なチェックと最低限の処置にとどまるため、より丁寧なクリーニングを希望すると追加料金が発生します。
最初は「検診だけだから安いはず」と思っていても、オプションが増えることで思った以上に費用がかかり、「高いな…」と感じる人が多いのです。
何度も通うと費用がかかるから
歯医者の定期検診は3〜6ヶ月に1回受けるのが理想と言われています。
1回の検診が2,500円〜5,000円だったとしても、年間で10,000円〜20,000円ほどかかる計算になります。
さらに、検診で虫歯や歯周病が見つかると、その治療で通院回数が増え、結果的に費用がどんどんかさんでしまうことも。
例えば、初期の虫歯治療なら1,500円〜3,000円ほどですが、神経の治療が必要になると20,000円以上かかることもあります。
また、歯石の除去や歯周病の治療は1回では終わらず、複数回の通院が必要になることが多いです。
最初は「検診だけのつもりだったのに、気づけば何度も通うことになっていた…」というケースもよくあります。
治療の積み重ねで、「やっぱり歯医者ってお金がかかるな…」と感じてしまうのかもしれません。
自費診療と保険診療の違いが分かりにくいから
歯医者の費用が「高いな」と感じる理由のひとつが、保険診療と自費診療の違いが分かりにくいことです。
保険が適用されるのは、虫歯や歯周病の治療、歯石取りなどの最低限の処置に限られます。
一方で、予防のためのクリーニングや、見た目を整えるホワイトニングなどは保険が使えず、全額自己負担になってしまいます。
そのため、「検診だけのつもりが、思ったより高くなった…」と驚くこともあるのです。
さらに、同じ定期検診でも、歯医者によって保険が適用される範囲が違うことがあります。
「かかりつけ歯科医機能強化型診療所」という認定を受けている歯医者なら、通常より充実したケアを保険の範囲で受けられることもありますが、そうでない歯医者では自費診療になってしまうことも。
自費診療と保険診療の仕組みが分かりにくいため、「説明を聞いたけど、結局なんでこんなに高いの?」と感じてしまう人が多いのが実情です。
実際いくらかかる?定期検診の費用相場
歯医者の定期検診の費用は、保険適用か自費診療かで大きく変わります。
一般的に、保険診療なら3,000円前後ですが、追加検査があると費用がさらにかかります。自費診療では1万円以上になるケースもあります。
保険適用なら3,000円程度が一般的
歯医者の定期検診は、基本的に健康保険が適用されます。
自己負担額は3割負担の場合で2,500円〜3,000円くらいが一般的です。歯や歯ぐきのチェック、歯石や歯垢の除去、歯磨きの指導などが含まれます。
ただし、歯の状態によっては、歯周病の検査や追加のクリーニングが必要になることもあり、その分の費用がかかることもあります。
定期検診の目安は3〜6ヶ月に1回とされていますが、こまめに通うことで虫歯や歯周病を予防し、大きな治療をせずに済む可能性が高まります。
レントゲンや追加検査で費用がかかることも
定期検診の基本料金は3,000円程度ですが、レントゲン撮影や追加の検査をすると、費用が増えることがあります。
例えば、レントゲンを撮ると1,000〜1,500円ほど上乗せされるケースが多く、歯ぐきの状態を調べる歯周病検査や、歯石をしっかり取るクリーニングを受けると、さらに費用が加算されることがあります。
また、前回の検診から長い期間が空いていると、歯の状態を詳しく確認するために追加検査が必要になることもあります。
例えば、歯周病の進行度を測る歯周ポケットの検査は、オプション扱いとなるケースもあり、保険が適用されても別途費用がかかることがあります。
自費診療なら1万円以上になるケースも
保険適用の定期検診は3,000円ほどですが、自費診療の場合は1回あたり10,000円以上かかることもあります。
自費診療は、より丁寧なクリーニングや、歯を白くするホワイトニング、虫歯や歯周病を予防するための特別なケアが含まれることが多いため、費用が高くなる傾向があります。
例えば、PMTC(プロによる徹底した歯のクリーニング)は、8,000円〜15,000円ほどかかることがあります。
また、歯科ドック(歯の総合検診)を受ける場合、検査内容によって10,000円〜50,000円と大きく差が出ることもあります。
自費診療は費用が高くなりがちですが、より質の高いケアを受けられるのが魅力です。
定期検診をもっと安く受ける方法
保険適用の歯医者を選ぶのが基本
定期検診の費用を抑えたいなら、保険適用の歯医者を選ぶことが大前提です。
日本では、ほとんどの歯科医院で保険診療を受けられますが、中には自由診療のみのクリニックもあるので注意が必要です。
保険が適用される定期検診では、虫歯や歯周病のチェック、歯石除去、歯磨き指導などが含まれることが多く、3,000円前後で受けられます。
ただし、レントゲン検査や特別なクリーニングが必要になると追加料金がかかる場合もあるので、事前に確認すると安心です。
また、歯科医院によって診療方針が異なり、同じ保険診療でも検査内容や料金に若干の違いが出ることがあります。
自治体の無料検診を活用しよう
自治体によっては、無料または低価格で受けられる歯科検診を実施しています。
例えば、40歳、50歳、60歳、70歳のタイミングで受けられる「歯周疾患検診」は、多くの自治体で行われており、無料または自己負担が少なく済むケースが多いです。
また、妊娠中の方を対象にした「妊婦歯科検診」を無料で受けられる自治体もあります。
妊娠中はホルモンバランスの変化で歯周病のリスクが高まるため、体調を気遣いながら負担を抑えて口腔ケアを受けることができます。
さらに、健康保険組合によっては、年に1回の定期検診費用を補助する制度を設けていることもあります。
例えば、会社員向けの健康保険では、自己負担を軽減する補助金が出るケースもあるので、加入している健康保険の内容を一度確認してみると良いでしょう。
定期検診の頻度を適切にコントロールする
定期検診は一般的に3ヶ月〜6ヶ月に1回が推奨されていますが、自分の口の状態に合わせて頻度を調整することで、費用の負担を抑えることができます。
例えば、虫歯や歯周病のリスクが低く、毎日のセルフケアがしっかりできている人は、半年から1年に1回でも十分な場合があります。
一方で、歯石が付きやすい人や、過去に歯周病の治療を受けたことがある人は、間隔を空けすぎるとトラブルの発見が遅れ、かえって治療費が高くなることもあります。
また、定期的に通う患者向けに割引制度を設けている歯医者もあるため、そういったサービスを利用するのもおすすめです。
適切な頻度で検診を受けることで、長期的に見ても医療費の節約につながり、歯の健康を維持しやすくなります。
どのくらいの間隔で通うのがベストかは、人それぞれ異なります。まずは歯医者さんと相談し、自分に合ったペースを見つけることが大切です。
高額にならない!歯医者選びのポイント

歯医者の選び方次第で、定期検診の費用を抑えられることがあります。
料金が分かりやすく、自費診療と保険診療の違いをしっかり説明してくれる歯医者を選ぶのがポイントです。予防歯科に力を入れているかもチェックすると安心です。
料金が明確な歯医者を選ぼう
定期検診の費用が思ったより高いと感じることはありませんか?
そんなときは、料金が明確な歯医者を選ぶのが大切です。
保険診療の料金は全国で決まっていますが、歯科医院によって検査や処置の内容が少しずつ違い、追加料金がかかることがあります。
特に自由診療(自費診療)になると、医院ごとに費用が大きく変わるため、事前にしっかり確認することが大事です。
最近は、ホームページや院内の掲示で料金表を公開している歯医者も増えているので、事前にチェックしてみましょう。
また、初回の診察時に、どの治療が保険適用で、どこからが自費診療になるのか、しっかり説明してくれる歯医者を選ぶと安心です。
予防歯科に力を入れているかチェック
定期検診を受けるなら、虫歯や歯周病を未然に防ぐ「予防歯科」に力を入れている歯医者を選ぶのがおすすめです。
予防歯科では、歯のクリーニングや歯磨きのアドバイスを通じて、治療が必要になる前に健康な歯を守ることを目指します。
また、定期検診の間隔も、一律に「○ヶ月ごと」と決めるのではなく、その人のお口の状態に合わせて提案してくれる歯医者の方が、無駄なく通えます。
例えば、虫歯や歯周病のリスクが低い人なら半年に1回、高い人なら3ヶ月に1回が目安です。
「治療のために通う」のではなく「歯を守るために通う」歯医者を選ぶことで、長い目で見て費用を抑えながら健康な歯を維持できます。
まとめ
定期検診の費用は、歯医者の選び方や検査の内容によって変わります。
保険が適用されれば費用は抑えられますが、レントゲンや追加のクリーニングを受けると少し高くなることもあります。
できるだけ負担を減らすには、料金が分かりやすい歯医者を選んだり、自治体の検診制度を活用したりするのがおすすめです。
こまめにケアを続けることで、大きな治療を避けられることも多く、結果的にトータルの医療費を抑えることにつながります。
当院は武蔵小金井駅から徒歩6分の立地にある地域密着型の歯医者です。
マイクロスコープを使った精密な診療で、できるだけ削らず、歯を大切にした治療を行っています。
「歯医者は痛くてこわい…」という方にも安心して通っていただけるよう、痛みに配慮したやさしい治療を心がけています。
また、院内はバリアフリーなので、小さなお子さんからご高齢の方まで安心です。
近年では「予防こそ最良の治療」との考えのもと、特に予防歯科にも注力しております。
お口の健康が気になる方は、ぜひ気軽にご相談ください!